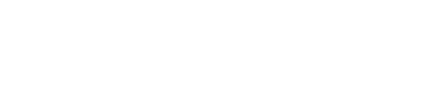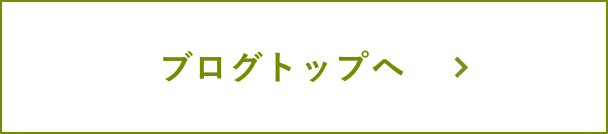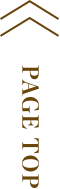リフォーム工事では、下地調整にとても時間と手間がかかります。
けれど、この下地は最終的に壁や仕上げ材で隠れてしまうため、どんなに丁寧に作業しても、完成後にはその苦労が見えなくなってしまうのです。
暮らしをつくろう。大切な人との時間を豊かに。
4代目の新野恵一(にいのけいいち)です。
(*タグで絞り込み→「4代目」を選択すれば、ブログがのぞけます。)
水平・垂直は当たり前ではない
建築物というのは、完全な水平・垂直ではありません。
「水平垂直が当たり前」と思われがちですが、実際はほとんどの家に少なからず歪みがあります。
この歪みをそのままにしてリフォームを進めると、あとで造作家具や建具を取り付ける際にズレや隙間が生じることも。
だからこそ、大工さんが木下地を組む段階で、できる限り歪みを取り、水平・垂直を整える作業が欠かせません。
このときに使うのが「胴縁(どうぶち)」と呼ばれる木材です。
この胴縁が、壁の垂直を保つための大切な役割を果たします。

Mさんの家のリフォーム現場から
現在進行中のMさんの家のリフォームでも、壁に歪みがありました。
特に造作家具を取り付ける部分の壁は、垂直精度が求められます。
そこで大工さんが一工夫。

柱に直接ボードを貼るのではなく、
柱とボードの間に胴縁を入れて、
この木で微調整しながら垂直を出していきます。
この作業、見た目以上に大変なんです。
クロスの貼り替えのような簡易な修繕では、ここまで丁寧な調整は行いません。
下地を整えるという見えない職人技
壁をはがして下地を直す——
これは、リフォームの中でも非常に手間のかかる工程です。
でも、ここを丁寧に行うことで、
仕上がりの美しさや、家具の納まりが格段に良くなります。
現場見学の際には、そんな「見えなくなる部分」にこそ大工の技が光っている、
という視点で見てみると面白いかもしれません。