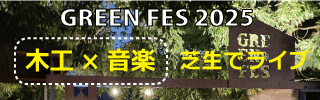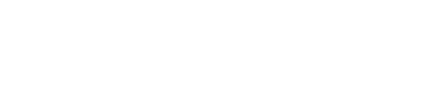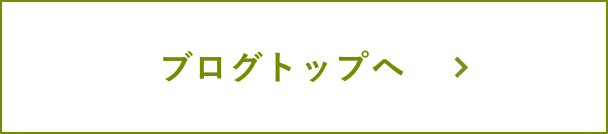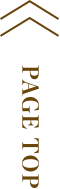aisuの家は、大きく暮らすことを目指しています。
鍵は、ふたつ。
体積をどう使うか。
空いている場所を見つけ、そこに開くこと。
暮らしをつくろう。大切な人との時間を豊かに。
4代目の新野恵一(にいのけいいち)です。
(*タグで絞り込み→「4代目」を選択すれば、ブログがのぞけます。)
限られた敷地で、大きく暮らす。2つの工夫。
家づくりにおいて「広さ」は、単に床面積だけではありません。
敷地が限られているからといって、窮屈な間取りになるとは限らないのです。
大切なのは、空間をどう使うか。
限られた条件の中でも、のびやかに、豊かに暮らすための工夫はあります。
今回は、そんな工夫の中でも、特に効果的な2つをご紹介します。
① 体積をめいっぱい使う
家の広さは「平面」だけでは測れません。
高さ=体積をどう活かすかによって、家の印象も、快適さも、大きく変わってきます。
天井を省き、ロフトとつなげる、階段と空間を連動させる。
こうした立体的な設計によって、単なる面積以上の広がりや、動きのある空間が生まれます。

たとえば【aisuの家】愛犬と一緒に暮らす家では、ロフトと2階をつなげ、エアコンも1台で済む設計に。
限られた床面積の中で、体積を活かすことで「広がりのある暮らし」を実現しています。

aisuの家のVRでも、ご確認ください。
→https://myhomemarket.jp/town/irimasa/aisu/vrc
② 抜ける場所を見つけ、そこに大きく開く
もうひとつの工夫が、視線の抜けをつくること。
住宅地では、周囲を家に囲まれていることも多く、「抜け」をつくるのは簡単ではありません。
だからこそ、敷地の中にあるわずかな隙間、視線が伸びていく方角を見極めることが重要です。
たとえば1階では、南北に空間を連ねながら、視線が遠くまで通る位置に大きな開口部を設けました。
そうすることで、視界も抜け、さらに自然光が最大限入り、面積以上の広がりと開放感を感じられるようになります。

これは「広くつくる」のではなく、「広く感じる」ための工夫です。
大きく暮らす、ということ
体積を活かすこと。
抜けに向かって開くこと。
この2つの設計的工夫によって、
限られた敷地の中でも、「大きく暮らす」という空間が実現できます。
狭さを制限ととらえるのではなく、
可能性を引き出す前提条件としてとらえること。
その視点が、住まいの自由度と快適性を大きく変えます。
限られた条件の中で、広さを生み出す。
それは、建築の面積で解決するのではなく、外部との関係や内部空間をデザインすることで導くものだと、私たちは考えています。