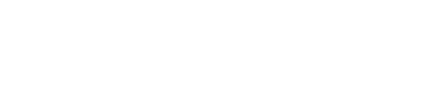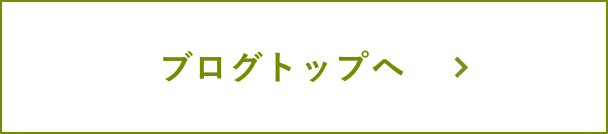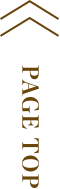「ちょうどいい家の大きさ」は、どれくらいですか?
実は、この「ちょうどいい」は、人によって全く違います。
そして、面積だけでは決まらないのです。
暮らしをつくろう。大切な人との時間を豊かに。
4代目の新野恵一(にいのけいいち)です。
(*タグで絞り込み→「4代目」を選択すれば、ブログがのぞけます。)
「奥さんは今の家の大きさに満足していますか?」
ある方に、そう聞かれて奥さんに尋ねてみたら
「大きすぎず、ちょうどいいよ」との答え。
でも、面積だけを聞いた人からすれば「それじゃ足りない!」と感じたのかもしれません。
実際、家の「ちょうどいい大きさ」は人によって違います。
さらに言えば、外部環境や、家のつくり方によっても違ってきます。
面積だけでは測れない広さ
家の広さは数字だけでは決まりません。
上下階のつながりや外とのつながりで、視覚的な広がりは変わります。
窓の位置によっても、空間の感じ方は大きく変化します。

大きさとコストのバランス
建物の床面積を大きくすると、建築費は上がります。
(*逆に小さくすると、坪単価は高く見えることもあります。水回りの数は変わらないため、どうしても割高に見えるのです。)
「こんな家がいい!」と思っても、予算とのバランスが崩れれば現実的ではありません。
そこで大切なのは、ファーストプランから、最終形態に至るプロセスの中で、ジブンにとって、ちょうどいい大きさを知ること。
諦める=明らかにする
「諦める」という言葉はネガティブに聞こえますが、本来は「明らかにする」という意味。
つまり、予算の中で何ができるかをはっきりさせることです。
我が家は3階まで使って29坪。
小さいと感じる人もいるでしょうが、私たちにはこれが心地いい。
いつも手が届く。そのくらいの大きさが、ぼくたちにとってはちょうどよかった。

シンプルにする難しさ
コンパクトな家を心地よく仕上げることこそ、家づくりの醍醐味だと思います。
けれど、それが一番難しい。
広くするのはいくらでもできますが、シンプルにまとめるのはもっと難しい。
シンプルとは、「自分だけでなく、誰が使っても使いやすい」状態のこと。
使い方を限定せず、暮らしの変化にも柔軟に対応できることが大切。今だけじゃないよね。
シンプルにしていく過程では、徐々に贅肉がそぎ落とされます。
「本当にこの面積が必要なのか?」と、いちいち自問自答することになります。
そうやって時間をかけても、最後に出てくるのはたった1案です。
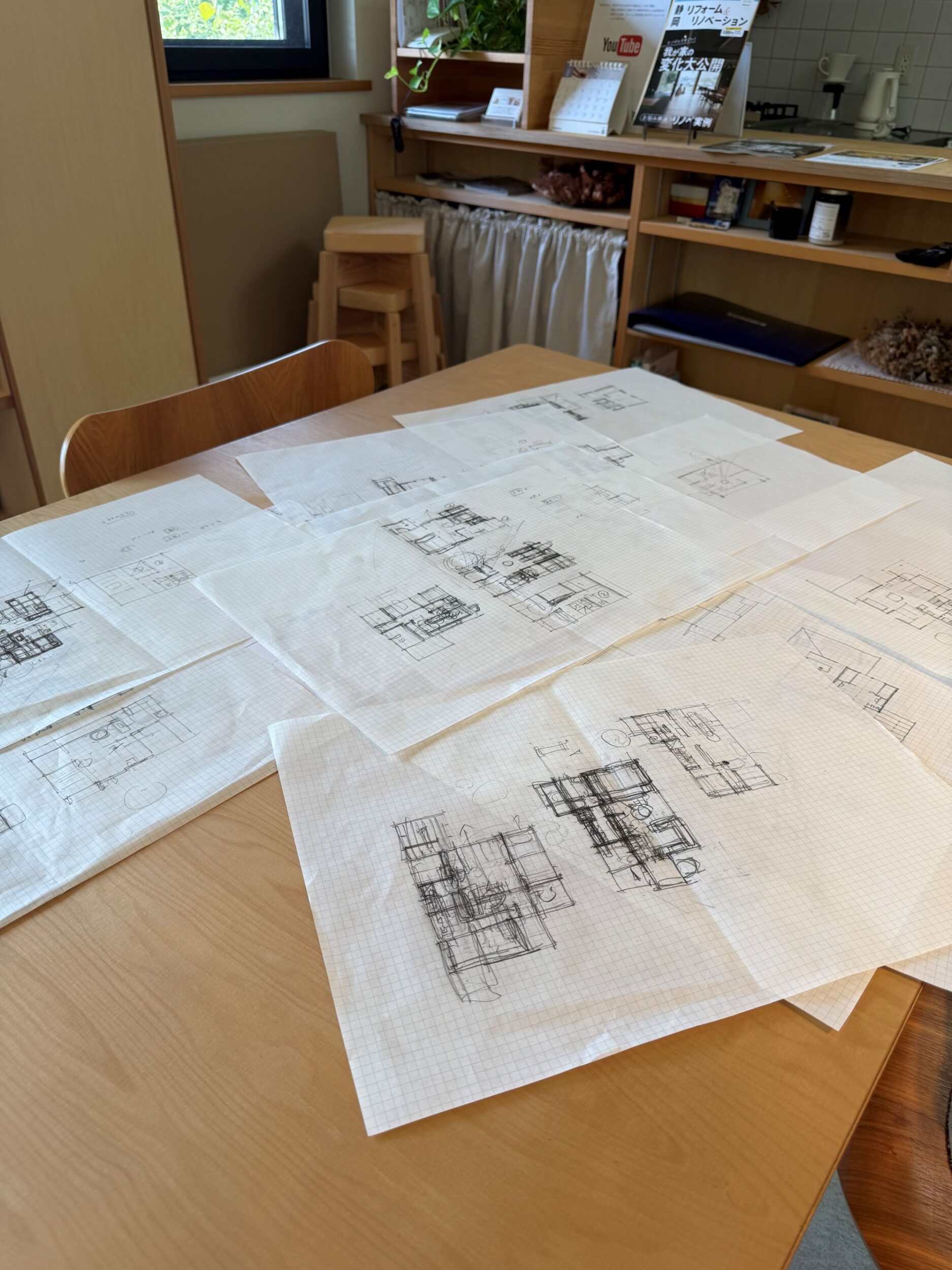
シンプルで心地よいものには、必ず納得感があります。
一方で、なにか違うと感じるものは、たとえ心地よくてもシンプルではないことが多い。
シンプルでないと、フレキシビリティ(柔軟性)も生まれにくいのです。
まとめ
家の大きさは、数字や坪数だけで決められるものではありません。
そこに暮らす人の価値観や予算、敷地条件によって「ちょうどいい」は変わります。
広ければいいわけではないし、小さければいいわけでもない。
大切なのは、自分たちにとっての「ちょうどいい大きさ」を見極めること。
そして、その大きさの中でシンプルに、心地よく仕上げること。
「これでいい」ではなく「これがいい」と思える家は、まず「諦める」ことから始まります。
諦めることで、本当に必要な広さや空間が明らかになり、そこから自分たちだけの心地よさを形にできるのです。
無理して広さを追いかけるより、まず予算の中で大きさを決める。
その大きさの中に、ジブンらしい空間をつくっていく。
それこそが、本当に豊かな暮らしにつながります。

「aisuの家」のオープンハウスが開催中です。
23坪の面積を、どのように使っているか。
LDKや、水廻りの配置によって、面積の割に大きなLDKが実現しました。
ご興味ある方、是非お越しください。
ちょうどいい大きさのヒントになるかも?しれません。