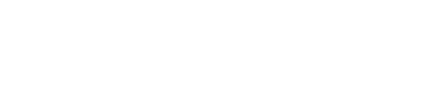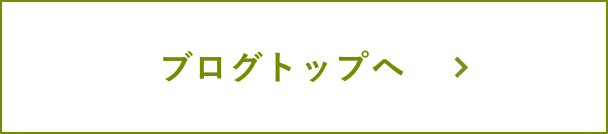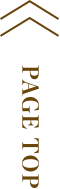湿気が気になる季節になると、
「家にカビが生えたらどうしよう」「床下って大丈夫かな?」と、建物への不安を感じる方も多いと思います。
特に梅雨どきは、空気が重たく、なんとなく家の中までジメジメしてくる感じがしますよね。
ぼくたち入政建築では、そんな季節でも安心して暮らせるように、湿気をためこまない家づくりを意識しています。
そのひとつが、基礎断熱という工法です。
暮らしをつくろう。大切な人との時間を豊かに。
4代目の新野恵一(にいのけいいち)です。
(*タグで絞り込み→「4代目」を選択すれば、ブログがのぞけます。)
■ 基礎断熱は湿気に強い? でも“空気の動き”がカギ
基礎断熱とは、床下を断熱して「室内と同じ空間」として扱う工法です。
外からの湿った空気が床下に入りにくく、カビの発生リスクを抑えるという大きなメリットがあります。
ただし、断熱だけで湿気を防げるわけではありません。
空気が動かず滞ると、湿気がこもってしまうこともあるため、空気の流れをきちんと設計することがとても大切です。

■ 入政建築がしている“湿気対策”の工夫
ぼくたちは、家の中も床下も、空気をしっかり動かす仕組みを整えています。
- びおソーラーを採用している家の場合
→ 太陽の熱で床下の空気を温め、室内へ循環させる仕組みになっています。 - びおソーラーがない家の場合
→ 床下に換気扇を設置し、空気を定期的に入れ替える工夫をしています。
これにより、湿気がこもりにくく、床下の状態も健やかに保つことができます。

*びおソーラーの場合
■ 梅雨時は「びおソーラー」を止めるのがおすすめ
びおソーラーは、自然エネルギーを活用した画期的な仕組み。
冬は室内に暖かさを届け、夏は外気をうまくコントロールしてくれる頼もしい存在です。
ただし、運転の判断基準は「温度」であり、湿度は感知しません。
- 冬モード:25℃以上で取り入れ開始、20.5℃以下で停止
- 夏モード:30℃以下で取り入れ開始、34.5℃以上で停止
そのため、梅雨時のように湿度が高くても、温度だけで取り込みを始めてしまうことがあるのです。

■ 対策は「停止」または「循環モード」
この時期は、びおソーラーを「停止」、もしくは「循環モードのみ」で運転するのがおすすめです。
(*循環運転は、ロフト部分の空気を床下に送る運転です。循環モードはオプションなので、ついていない施工事例も多くあります)
外の湿った空気を取り込まず、家の中の空気だけをやさしく動かすことで、床下の空気が滞留するのを防ぎます。
■ でも、やっぱり気持ちいいのは「窓を開ける」こと
ここまでお話ししてきたのは、窓を閉めた状態での湿気対策。
でも、やっぱり一番気持ちいいのは――窓を開けて、風を通すこと。
晴れた日や、湿度が落ち着いた朝には、
思いっきり窓を開けて、家の中に風を通すのが、いちばんのリフレッシュです。

湿気は、完全に避けることはできません。
でも、構造・設備・暮らし方の工夫で、しっかりつきあっていくことができます。
入政建築では、
- 基礎断熱で湿気を入りにくくし、
- 空気を動かす仕組みでこもらせず、
- びおソーラーや住まい手の工夫で自然と向き合う
そんな家づくりを、大切にしています。
湿気と向き合いながら、
風の通る、気持ちのよい暮らしを一緒につくっていきましょう。